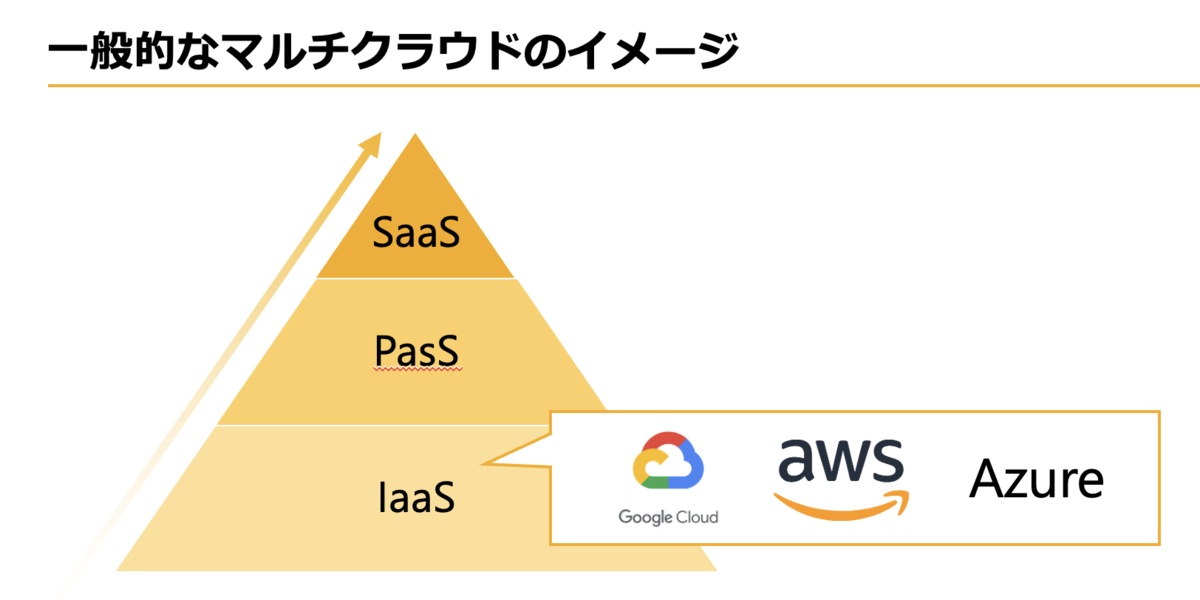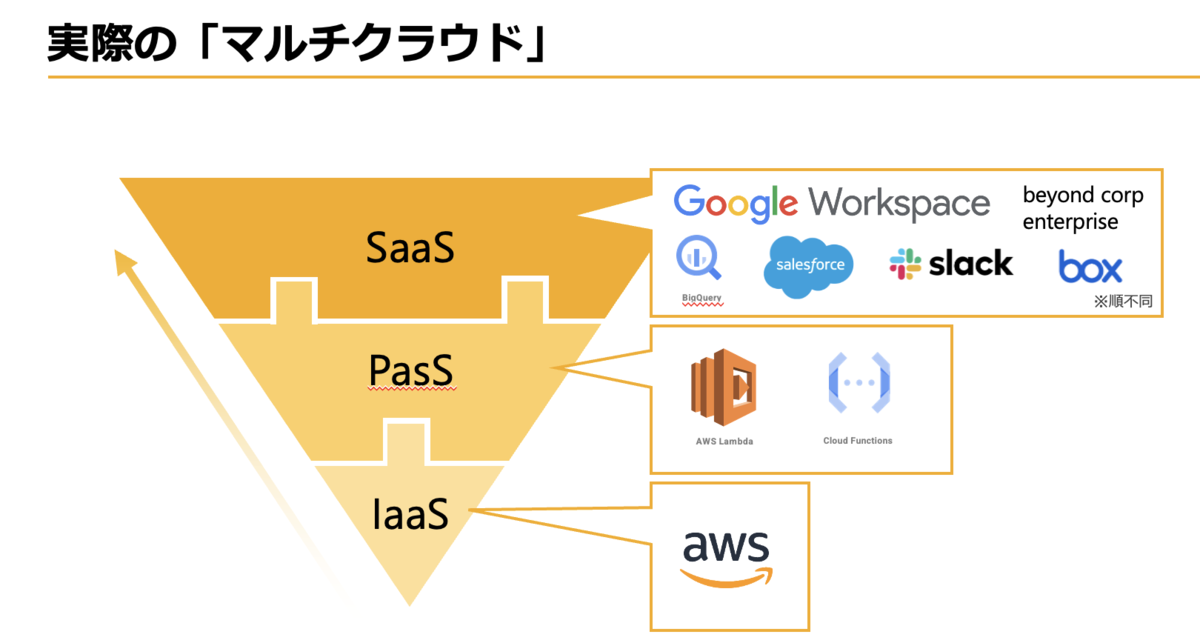新年あけましておめでとうございます。
こちらのブログもすっかり「年頭挨拶だけ更新する」という悪習が定着してしまい各方面から「社長ブログはどうなっているのか」というお叱りを頂戴しております。
特に2023年はコロナの影響もだいぶ軽減され会食の席も増えたことから、久方ぶりにお目にかかる方も増えたのですが、そうした方々から「社長ブログを更新してくれていれば大石さんの近況が分かるのに、(コロナで疎遠になっていたこともあり)ブログがないと本当に近況が分からない」というお声をいただいたことがだいぶ心に響きました。
どうしても社長ブログには「それなりのいいことを書こう」と思って準備する一方で筆(キーボード)が遠のいてしまいがちですが、近況を書き残しておくだけでも情報としてお役に立てることがあるなら吝かではありませんので、2024年は定期的に近況のご報告をするようにして参りたいと思います。
事業のご報告は上場以降「決算説明会」の方に場を譲っておりますが、皆様のお陰を持ちまして順調に進捗しております。これもひとえに、日頃より当社をご愛顧くださっているお客様、パートナーのみなさま、素晴らしいサービスを提供してくれているAWS、Googleの皆さま、そして成長を支えてくれている社員と、そのご家族・パートナーの皆さまのお陰と深く感謝致しております。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
2023年は生成AI元年とも言える年でしたが、当社もご多分に漏れず全グループ社員が利用できるように制度をつくり、いくつかのパイロットプロジェクトを走らせるだけでなく、実際のお客様が安全に生成AIを利用できるような環境づくりのプロジェクトにも参画させていただきました。私も実際に手を動かして試しておりますが、率直に言うと「意外と難しい」という感想です。ChatGPTが出たての「何でもできそうだ」という万能感は一段落し、どのエンジンをどのように使い、かつ企業固有のデータをどのようにRAGで読み込ませるのかという組み合わせの問題が予想より複雑で一筋縄ではいきませんでした。
社内では「当社はこれからCIerからAIerになっていく」という話をしていますが、まさにAIもインテグレーターが必要な複雑系の世界に突入していきそうです。こうした状況でも、クラウドを用いてお客様の課題に真正面から取り組み「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」というビジョン目指して社員一同力を合わせて参ります。
今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。